|
|
�㏞�����̎葱��
�i1�j�㏞�����̈Ӌ`
�@�������Y�ƂȂ����ЂƂ̓y�n�����Y���z�̑啔���ł�������A�푊���l�̎��Ƃ����p���鑊���l���擾���ׂ����Y���唼���߂�ȂǁA�������Y�̎�ނ���ɂ���Ă͌�������������ł��邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B
�@���̂��߁A����̑����l���������Y�̑S�����͑啔�����擾���A���̑����l���瑼�̑����l�ɋ��K���̎��Y����t����A�Ƃ�����Y���������p����Ă��܂��B����̑����l�����̑����l�ɑ㏞�����x�����Ƃ����Ӗ��ŁA��ʓI�ɑ㏞�����Ƃ��Ă��܂��B
�@�㏞�����́A���Ƃ��ƉƎ��R���K���ɂ�����u�ƒ�ٔ����́A���ʂ̎��R������ƔF�߂�Ƃ��́A��Y�̕������@�Ƃ��ċ��������l�̂P�l���͐��l�ɑ��̋��������l�ɑ��č��S�����āA�����������Ă��镪���ɑウ�邱�Ƃ��ł���v�Ƃ����K��������Ƃ��A�R�������ō̗p����镪�����@�ł��B�����A�����I�ɂ͑����l�Ԃ̗��Q�̒����ɗL���Ȃ��߁A���c�����ɂ����Ă����p�Ⴊ���������܂��B
(�Q)�㏞�����̎�����̗��ӓ_
�@�����l�Ԃ̋��c�ő㏞�������s���ꍇ�́A�㏞���z�̌���͂������̂��ƁA���̑㏞�����x���������l�i�㏞���̕��S���j�̎x���\�͂��������邱�Ƃ��d�v�ł��B�������c���������Ă��A�㏞���̎x�����s�\�̏ꍇ�͌���Ƀg���u�����������˂܂���B
�@�����I�ɂ́A�㏞���̎x���\�͂����ɂ߂���Ŏ��s���邱�ƂƂ��A�㏞���̎x��������x�����@������Y�������c���ɖ��L���Ă����ׂ��ł��傤�B
�@���̏ꍇ�́A�㏞���̎x�������܂ł̊��Ԃ̐ݒ��x���������Ƃ��邱�Ƃ����ӂ���Ή\�ł����A�g���u����������邽�߂ɂ́A�Ȃ�ׂ��Z���Ԃ̂����Ɉꊇ�����Ƃ��邱�Ƃ��]�܂�܂��B
�@�Ȃ��A�x�����������Ԃɂ킽��ꍇ�́A�㏞���̗��s��S�ۂ��邽�߂̑[�u�i�㏞���x���҂̎��Y�ɑ������̐ݒ�Ȃǁj���l������K�v������ł��傤�B
�Q.�㏞�����̐Ŗ����
(�P)�㏞�����Ƒ����ł̉ېʼn��i�v�Z
�@�����ł́A��Y�����ɂ��擾�����e�����l�̍��Y���z�����Ƃɉېł��邱�Ƃ������Ƃ��Ă���A���̓_�͌��������ł��㏞�����ł��ς��܂���B�����A�㏞�����ɂ��ẮA�����ł̉ېʼn��i�̌v�Z�ɓ��ʂȎ戵������߂��Ă��܂��B
�@�㏞�������ȗ������Ă����A���������l���`�Ƃa�̂Q�l�i�������͂�������Q���̂P�j�������Y�͓y�n�݂̂Q���~�A�Ƃ����ꍇ�ɁA�y�n�̑S���𑊑��l�`���擾���A�`����a�ɂP���~�̋��K���x�����Ƃ������@�ł��B
�@���̏ꍇ�A�����l�a���`����擾������K�P���~�́A�푊���l���瑊���ɂ��擾�������Y�ł͂���܂��A�����ł̉ېŏ�͑������Y�Ƃ݂邱�Ƃ��K���ł���A����̑����l�`�̑������Y�́A�����I�ɂ͓y�n�Q���~����㏞���P���~���T�������P���~�Ƃ���̂����R�ł��B���̂��߁A�����ł̉ېʼn��i�̌v�Z�ł͎��̂悤�Ɏ�舵�����ƂƂ��Ă��܂��B
�@�㏞���Y�̌�t������
�@�ېʼn��i���������͈②�ɂ��擾�������Y�̉��z�{�㏞���Y�̉��z
�A�㏞���Y�̌�t��������
�@�ېʼn��i���������͈②�ɂ��擾�������Y�̉��z�|�㏞���Y�̉��z
�@�Ȃ��A���̎Z���ɂ�����u�㏞���Y�̉��z�v�́A�㏞���̊z�̑����J�n���̋��z�ɂ��܂��B�㏞�����ɂ���t���鎑�Y�����K�i�����j�łȂ��A�y�n�Ȃǂ̌����ł���ꍇ�ɂ́A��Y�������łȂ������J�n���̉��z�ŏ�L�́u�㏞���Y�̉��z�v���Z�肷��Ƃ����Ӗ��ł��B
�@���Ƃ��A�����l�`�������l�a�ɁA�`���L�̓y�n�������đ㏞����ꍇ�A�y�n�̕]���z�������J�n���łP���~�A��Y�������łP���Q�疜�~�Ƃ����Ƃ��́A��L�Z���́u�㏞���Y�̉��z�v���P���~�Ƃ���Ƃ������Ƃł��B�@
(�Q)�㏞���Y�̉��z�̒����v�Z
�@�Ƃ���ŁA�㏞�������s��ꂽ�ꍇ�̑����ł̉ېʼn��i�̌v�Z�ɂ��āA��L�́u�㏞���Y�̉��z�v�̎Z���A�u�����v�Ɓu�����ŕ]���z�v�̊J���Ɋւ����肪����܂��B
�@���Ƃ��A�����ŕ]���z�Q���~�̓y�n�S�����擾���������l�`���瑊���l�a�ɑ㏞���P���~����t�����Ƃ����ꍇ�A�`�̎擾�����y�n�́u�����v���Q���T�疜�~�ł���Ƃ���A�`�͎����I�Ɂi�Q���T�疜�~�|�P���~���P���T�疜�~�j�̍��Y���擾�������ƂɂȂ�܂��B
�@���̏ꍇ�A�y�n�̑����ŕ]���z�Q���~�����ƂɁA
�@�@�`�̉ېʼn��i�@�@�Q���~�|�P���~���P���~�i�������O�D�T�j
�@�@�a�̉ېʼn��i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P���~�i�������O�D�T�j
�Ƃ���ƁA���ΓI�ɂ`�͐ŕ��S���y������A�a�͉ߏd�ƂȂ�܂��B���̂��߁A�����Ƒ����ŕ]���z�̊J�������邽�߁A�㏞���Y�̉��z�i�`����t���A�a���擾����P���~�̋��K�j�����ɂ��Z�肵�Ă���ꍇ�́A���̉��z�����ƂƂ��ĉېʼn��i���v�Z���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���������l���̑S���̋��c�Ɋ�Â��đ㏞���Y�̉��z�����̇A�̎Z���ɏ����āA���͍����I�ƔF�߂�����@�ɂ���Čv�Z���Đ\�������ꍇ�E�E�E���̐\�������������z
�A�@�ȊO�̏ꍇ�ŁA�㏞���̊z���A�㏞�����̑ΏۂƂȂ������Y�����肳��A���A���̍��Y�̑㏞�����̎��ɂ�����ʏ�̎�����z�i�����j����Ƃ��Č��肳��Ă���Ƃ��E�E�E���̎Z���ɂ��v�Z�������z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㏞���Y�̑ΏۂƂȂ������Y��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����J�n���̑����ŕ]���z
�㏞���Y�̉��z���㏞���̊z�~�@----------------------------
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㏞���̊z�̌���̊�ƂȂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㏞�����Ώۍ��Y�̑㏞�����̎��̎���
�@���̂����A�̎Z���ɂ��āA�O�q�̑����l�`�Ƃa�̗�Ŏ����ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B
�@�@�E�㏞���Y�i���K�P���~�j�̉��z
�@�@�@�@�@�@�i�㏞���̊z�j�@�@�@�i����̓y�n�̑����J�n���̑����ŕ]���z�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���~
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P���~�~�@�@�@�@-----------------------�@�@�@���W�疜�~
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���T�疜�~
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�`�̎擾�����y�n�̕������̎����j
�@�E�e�����l�̉ېʼn��i
�@�@�@�@�@�����l�`�E�E�E�Q���~�|�W�疜�~���P���Q�疜�~�i�������O�D�U�j
�@�@�@�@�@�����l�a�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�@�E�W�疜�~�i�������O�D�S�j
�@���ӂ������̂͏�L�@�ɂ�����u�����I�ƔF�߂�����@�v�ł��B�戵���̎�|�́A�[�Ŏ҂̈ӎv�d���A�C�ӂ̐\���z���F�߂�Ƃ������Ƃł��B����́A�㏞���Y�̉��z���ǂ̂悤�ɎZ�肵�Ă��A�ېʼn��i�̍��v�z�⑊���ł̑��z�͕ς��Ȃ��A�Ƃ����l���������邩��ł��B
�@���́A���������l���ɔz��҂�����ꍇ�ł��B�z��҂ɂ͐Ŋz�y���K�肪�K�p����܂����A�y���z�������グ�邽�߂ɑ㏞���Y�̉��z��s�����ȕ��@�ŎZ�肷��ƁA���̐\���͔۔F����邨���ꂪ����Ƃ������Ƃł��B
�@�Ȃ��A��L�A�̎Z���̕���̋��z�i�㏞�����̑ΏۂɂȂ������Y�̑����J�n���̑����ŕ]���z�j�̎Z���A���̍��Y�ɂ��āu���K�͑�n���̓���v���K�p�����ꍇ�́A���̓���K�p�O�̕]���z�ɂ��K�v������܂��B
(�R)�㏞���Y�������ł���ꍇ�̏��n�����ې�
�@�㏞�����ɂ���t���鎑�Y�����K�i�����j�̏ꍇ�͖�肪����܂��A�y�n�ȂǏ��n�����̊���ƂȂ鎑�Y�̏ꍇ�́A���n�v�ɑ���ېŖ�肪�����܂��B
�@�㏞���Y�̌�t�́A�㏞���̏��łƂ����Ή����̂�����n�ɊY�����܂��B���������āA�㏞���Y����t���鑊���l�����Ƃ��Ə��L���Ă����y�n���̎��Y�ő㏞����ƁA���̎��̎����ŏ��n�������̂Ƃ݂Ȃ���܂��B
|
|
|
|
|
|
|
| ���������Y�̏��p�Ɋւ���葱���̊T�v! |
�� �@���Ɋւ���葱���T�v
�� �Ŗ��Ɋւ���葱��
�� �����J�n��̃^�C���X�P�W���[�� |
| ���⌾��������ꍇ�̑Ή��Ǝ葱���I |
�� �⌾���̊J���ƌ��F
�� �⌾�̎��s
�� �⌾�̎�ނƈ⌾�����̖@�I����
�� ���M�؏��⌾
�� �����؏��⌾ |
| ���⌾�����̖@�I���́I |
�� �F�m��
�� �⌾�i�②�j�Ƒ����� |
| ���������Y�̔c���ƒ����̃|�C���g�I |
�� ���Y�����̕K�v��
�� ���Y�����̃|�C���g
�� �s���Y�̒����Ɠo�L�����ؖ����̎��W
�� �a�����E�L���،��̒����Ǝc���ؖ����̎��W
�� �����ی��_��E���Q�ی��_��̒����Ɗm�F
�� ���̑��̍��Y�̒����Ɗm�F |
| ����Y�����̕��@�I |
�� ��Y�����̈Ӌ`�ƌ���
�� ��Y�����̊�Ǝ���
�� �����̋�̓I���@
�� ��Y�����̒���ƐR��
�� ���������̎葱��
�� �㏞�����̎葱��
�� �㏞�����̐Ŗ����
�� ���������̎葱��
�� ���������̐Ŗ���� |
| �����K�͑�n���ɂ��Ẳېʼn��i�̌v�Z�I |
�� ����̎�|�ƊT�v
�� ���K�͑�n���̈Ӌ`
�� ����̓K�p�Ώۖʐρi���x�ʐϗv���j
�� ���z�̊���
�� ���莖�Ɨp��n��
�� ���苏�Z�p��n��
�� ���蓯����Ў��Ɨp��n��
�� �ݕt���Ɨp��n��
�� ������邽�߂̐\���葱���@ |
| �������ł̎d�g�݁I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�� �����ł͂ǂ��ɔ[�߂�ŋ��H
�� �����l�ƂȂ��l�́H
�� �����l�ƂȂ�Ȃ��l�́H
�� �����l�̑g�ݍ��킹�́A���ʂ�H
�� �ǂꂾ�����Y�����炦��́H
�� ���@�ŋK�肷�鑊����
�� �����ł̊�b�T���Ƃ́I
�� �����l�Ɩ@�葊���l�̋��
�� �����ł��ېł���錴���Ƃ́I
�� �[�ŋ`���҂̋敪�Ƃ́I
�� �����ł̉ېō��Y�Ƃ́I
�� �����ł̔�ېō��Y�Ƃ́I
�� �����ł̍��T���Ƃ́I
�� �����ł̎O�i�K�̌v�Z���@�Ƃ́I
�� �����ł̉ېʼn��i�̌v�Z�Ƃ́I
�� �����ł̑��z�̌v�Z�̂���܂�
�� �[�t�Ŋz�̌v�Z�̂���܂� |
| �����������Z�ېŐ��x�ɂ����鑊���ł̌v�Z |
�� �����ł̉ېʼn��i�̌v�Z
�� ���������Z�ېłƑ����J�n�O3�N�ȓ���
�@�@ ���^���Y�̉��Z�̊W
�� ���������Z�ېłɌW�鑡�^�Ŋz�̍T��
�� ���������Z�ېœK�p�҂�2�����Z
�� ���������Z�ېŐ��x�Ɨ�N�ېŕ����Ƃ̈� |
| �����Ə��p�Ő� |
�� ������Ƃ̎��Ə��p���
�� �o�c���p�~�����@�Ǝ��Ə��p���x
�� ���ꊔ���ɌW�鑊���ł̔[�ŗP�\���x
�� �F�菳�p��Ђ̗v��
�� �푊���l�Ƒ����l�̗v��
�� ����̑ΏۂɂȂ銔�����͈̔�
�� �����ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z���@
�� �[�ŗP�\�����̊m��ƗP�\�Ŋz�̔[�t
�� �P�\�Ŋz�̖Ə�
�� ����̓K�p����ꍇ�̎葱 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@ |
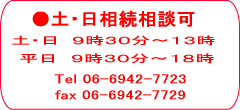

�@ |
|
|
�s����-���������������@
�V�ŗ��m�������@�ŗ��m�@�V�@����
���T�S�O�|�O�O�R�X�@���s�����擌���틴�Q�|�Q�S�|�Q�O�P
�s�d�k�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�R�@�e�`�w�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�X
�@�d���������F���������V�V�Q�R�������R�D�����|�������D�����D����
�@Co���������������i���j2006�r�������s�����`�������������������n�����������D�`�����q�����������q���������������D |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |