���⌾��������ꍇ�̑Ή��Ǝ葱���I
�� �⌾���̊J���ƌ��F
�� �⌾�̎��s
�� �⌾�̎�ނƈ⌾�����̖@�I����
�� ���M�؏��⌾
�� �����؏��⌾ |
���⌾��������ꍇ�̑Ή��Ǝ葱��
�⌾���̊J���ƌ��F
�@�������J�n�����ꍇ�ɂ́A�푊���l�Ɉ⌾�i�⌾���j�����邩�ۂ��𑁋}�Ɋm�F���ׂ��ł��B
�@���Y�̏����Ɋւ���⌾������ɂ�������炸�A�����l�Ԃň⌾�̎��s�ƈقȂ���Y�̕������s�����ꍇ�ɂ́A����Ɉ�Y�����̂�蒼�����̖�肪�����邩��ł��B
�@�⌾�҂�����ꍇ�ɂ����āA���̈⌾���ɕ�����Ă���Ƃ��́A�����l���͂��̑㗝�l������������ĉƒ�ٔ����ŊJ�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�܂��A�����؏��⌾�������A�⌾���͉ƒ�ٔ����́u���F�v���K�v�ł��B���F�Ƃ����̂́A�⌾���̓��e��̍ق��m�F���A�U����ϑ���h�~���邽�߂̌����葱���ŁA���̏؋��ۑS�̖ړI������܂��B
�@�⌾���ۗ̕L�҂͖��͔����҂́A�⌾�҂̏Z���n���NJ�����ƒ�ٔ����Ɂu�⌾�����F�\�����v�ƂƂ��Ɉ⌾�����o���܂��B�ƒ�ٔ����ł́A���̓��e�����m�F�̏�A���F�؏����쐬����܂��B
�@���̏ꍇ�̌��F�́A�ƒ�ٔ����ɂ��ۑS�̎葱���ł�����A�⌾���L�����������Ƃ������ƂƂ͊W������܂���B���ɂ��̈⌾��������̎҂ɋ�������č쐬���ꂽ���̂ŁA�⌾���{�l�̐^�ӂƈقȂ���̂ł������Ƃ��Ă��A�ƒ�ٔ����͂��̓��e�Ɋ֒m���܂���B�⌾���e�ɕs�M��s��������ꍇ�́A�⌾�̖����m�F�̑i�����ő����K�v������܂��B
�@�܂��A���Y�̏����ɂ��āA�◯���ɔ�������e�ł������Ƃ��Ă��A���̈⌾���͖̂����łȂ��A�ʓr�Ɉ◯�����E�������s�����ƂɂȂ�܂��B
�@�Ȃ��A����̂���⌾�����ƒ�ٔ����ȊO�̏ꏊ�ŕ�����A���F�̎葱����ӂ����ꍇ�́A�T���~�ȉ��̉ߗ��ɏ������܂��B |
�⌾�̎��s
�@�⌾�̓��e������������ɂ́A���܂��܂ȍ�Ƃ��K�v�ł��B�s���Y�̏��L���ړ]�o�L�A���Y�̈��n���A�F�m�Ɋւ���⌾�ł�����̓͏o�Ȃǂł��B�����̍�Ƃ����s���邱�Ƃ��⌾�̎��s�Ƃ����A���̔C�ɓ�����҂��⌾���s�҂Ƃ����܂��B
�@�⌾���s�҂́A�⌾�Ŏw�肷�邱�Ƃ��ł��܂����A�܂��A�⌾�ł��̎w����O�҂Ɉϑ����邱�Ƃ��ł��܂��B�w�肷��⌾���s�҂͈�l�ł������ł����܂��܂���B
�@���̏ꍇ�A�w�肳�ꂽ�҂͈⌾���s�҂ɏA�C����`���͂Ȃ��A���̎҂̏��F�ɂ��⌾���s�҂ƂȂ�A�܂��A���̏A�C�����ۂ��邱�Ƃ��ł��܂��B�w�肳�ꂽ�҂����̏A�C�����ۂ����ꍇ�A���邢�͈⌾�Ɉ⌾���s�҂̎w�肪�Ȃ������ꍇ�́A�����l���̗��Q�W�҂��ƒ�ٔ����Ɉ⌾���s�҂̑I�C�̐\���Ă����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�⌾���s�҂́A�⌾�葱���Ɋւ����̌�����L���܂�����A�����l�������̎��s��W���邱�Ƃ͂ł��܂���@�Ȃ��A�⌾���s�҂̕�V�́A�⌾�Œ�߂��Ă���ꍇ�͂���ɏ]���܂����A���̒�߂��Ȃ��Ƃ��́A�������Y�̏��ɂ��ƒ�ٔ��������肷�邱�ƂɂȂ�܂��B
�@���̏ꍇ�̕�V��⌾�̎��s�Ɋւ����p�́A�������Y�̒�����x�o����܂��B
|
�⌾�̎�ނƈ⌾�����̖@�I����
�i1�j�⌾�̎�ނƍ쐬���@
�⌾�̎��
1.���ʕ����⌾
�@���M�؏��⌾�A�����؏��⌾�A�閧�؏��⌾
2.���ʕ����⌾
�@��}���⌾-���S��}�҈⌾�A�D������҈⌾
�@�u��n�⌾-��ʊu��n�⌾�A�D���u��n�⌾
�@�@�@
���M�؏��⌾
�@�S�������M�Ƃ���B��M��[�v���Ȃǂō쐬�������͖̂����ƂȂ�B
�A���t�����M�ŋL������B���̏ꍇ�A�u�����Q�T�N�R���v�̂悤�Ɂu���v���L�����Ă��Ȃ����͖̂����ƂȂ�B�܂��A�u�����Q�T�N�R���g���v�Ƃ����̂������ƂȂ�B
�B���������M����B���̏ꍇ�A�y���l�[���Ȃǖ{���ȊO�ł��⌾�҂�����ł���ΗL���Ƃ���Ă���B
�C����́A���]�܂������A�F���d��ł��L���ł���B
�D���������́A���̉ӏ��m�ɂ��A���̉ӏ��ɉ���̏�A������v����B
�E�⌾���ɕ�������邩�ۂ��͔C�ӂł��邪�A����̂���⌾���͉ƒ�ٔ����ŊJ�����邱�Ƃ��`���t�����Ă���̂ŁA�U����ϑ���h�~����ϓ_����͕��邱�Ƃ��]�܂����B
�@�@�@
�����؏��⌾
�@�ؐl�Q�l�ȏ�ƂƂ��Ɍ��ؐl����ō쐬����i�⌾�҂̕a��Ȃǂɂ���ẮA���ؐl�Ɉ˗����Ď���͕a�@�Ȃnj��ؐl����ȊO�̏ꏊ�ō쐬���邱�Ƃ��\�j�B
�A�⌾�҂��⌾�̓��e�����ؐl�Ɍ��q����B
�B���ؐl���⌾�҂̌��q���e�i�⌾���e�j��M�L���A������⌾�ҋy�яؐl�ɓǂݕ�������B
�C�⌾�ҋy�яؐl���M�L���e�̐��m�Ȃ��Ƃ��m�F�E���F������A�⌾�ҋy�яؐl�̑S�����⌾���ɏ����E����B�i�⌾�҂��a�C�Ȃǂŏ����ł��Ȃ��Ƃ��́A���ؐl�����̗��R��t�L���ď����ɑウ��j
�D���ؐl�����̏؏���@���ɒ�߂�����ɏ]���č쐬�������̂ł���|��t�L���āA���̈⌾���ɏ����E����B
|
|
|
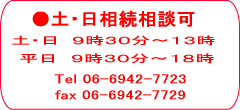

|
|
|
�s����-���������������@
�V�ŗ��m�������@�ŗ��m�@�V�@����
���T�S�O�|�O�O�R�X�@���s�����擌���틴�Q�|�Q�S�|�Q�O�P
�s�d�k�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�R�@�e�`�w�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�X
�@�d���������F���������V�V�Q�R�������R�D�����|�������D�����D����
�@Co���������������i���j2006�r�������s�����`�������������������n�����������D�`�����q�����������q���������������D |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |