|
|
���⌾�����̖@�I����
�@�⌾�ɂ���Ė@�I�Ȍ��͂�^������̂́A���Y�̏����Ɋւ���i�②�Ȃǁj�����Ɋւ��鎖���i�����w�蕪�Ȃǁj�y�ѐg���Ɋւ��鎖���i�⌾�ɂ��F�m�Ȃǁj�̂R�ɑ�ʂ��邱�Ƃ��ł��܂��B�⌾�łł��鎖�������ƁA���̂Ƃ���ł����A�����̂����A�K�v�Ȏ����������⌾���ɋL�ڂ���Α���邱�Ƃ͂����܂ł�����܂���B
�@�F�m
�A�㌩�l�̎w��A�㌩�ēl�̎w��
�B�②�A�s��
�C�②�̌��E���@�̎w��
�D�����l�̔p���A�p���̎����
�E�������̎w��A�w��̈ϑ�
�F���ʎ�v�҂̎��߂��̖Ə�
�G��Y�������@�̎w��A�w��̈ϑ�
�H��Y�����̋֎~
�I���������l�Ԃ̒S�ېӔC�̎w��
�J�⌾���s�҂̎w��A�w��̈ϑ�
�K�M���̐ݒ�
�@�Ȃ��A�����ȊO�̌l�̊���I�Ȏ����Ƃ��āA���Ƃ��u�������Y�͉~���ɕ��z���邱�Ɓv�Ƃ��A�u�����l�݂͌��ɏ��������Ă������Ɓv���邢�́u���V�͊ȑf�ɍs�����Ɓv�Ƃ��������Ƃ��⌾���ɏ������Ƃ͂��܂��܂���B�������A�@�I�Ȍ��͈͂����܂���B
���⌾�i�②�j�Ƒ�����
�@�⌾�ɂ����Y���^���u�②�v�Ƃ����A�A�②�����҂��u�ҁv�Ƃ����܂����A�҂̎擾���Y�ɂ��đ����ł��ېł���邱�Ƃ͂����܂ł�����܂���B�⌾�����́A�����łɊւ�邱�Ƃ����Ȃ��̂ł����A�Ƃ��Ɂu��Y�������@�̎w��v�Ɓu��Y�����̋֎~�v�������͑����łɑ傫�ȉe���������܂��B
�@�����ł́A��Y�����̕��@�ɂ���Ĕ[�t�Ŋz���قȂ邱�Ƃ�����A�܂��A���Y�̎�ނɂ���ẮA���̍��Y�̎擾�҂��N�ł��邩�ɂ���đ����l�S�̂̔[�Ŋz�ɉe�����y�ڂ����x������܂��B�O�҂́u�z��҂ɑ��鑊���Ŋz�̌y���v�ł���A��҂́u���K�͑�n���̓���v�ł��B
�@�푊���l�̔z��҂ɂ��āA�������Y���z�i�ېʼn��i�̍��v�z�j�̂����@�葊���������z���͂P���U�C�O�O�O���~�̂����ꂩ�������z�ɑΉ����鑊���Ŋz�͐Ŋz�T���ƂȂ�܂��B���̂��߈⌾�Ŕz��҂̎擾���Y���w�肵�A���̎w��ɏ]���ĕ����������ꍇ�ɔz��҂̎擾���Y���z�������̋��z�������ƁA���ʓI�ɐŊz�T�����\���Ɋ�������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�@�܂��A�푊���l�̎��Ɨp��n���⋏�Z�p��n���ɂ��ẮA���̎擾�҂����̎҂ł���ꍇ�ɂ́A�u���K�͑�n���̌��z����v�ɂ�肻�̑����ŕ]���z����W�O���̌��z���K�p�ł��邱�ƂƂ���Ă��܂��B�����̑�n���̎擾�҂��w�肵���ꍇ�A���̎擾�҂��W�O�����z�̓K�p�Ώێ҂łȂ��Ƃ���A��������������ꍇ�ɔ�ׁA�[�Ŋz���ߑ�Ȃ��̂ɂȂ�܂��B
�@���������āA��Y�������@���⌾�Ŏw�肷��ꍇ�͂��̂悤�ȐŖ����ɏ\���Ȕz��������K�v������܂��B
�@�܂��A�����ł̐\���́A�����l�������̊J�n��m�������̗�������P�O�����ȓ��Ƃ���Ă��܂����A�\�����̒�o���ɑ������Y����������Ă��Ȃ��ꍇ�́A�z��҂̐Ŋz�y������⏬�K�͑�n���̓���̂�������K�p�ł��Ȃ����ƂƂ���Ă��܂��B
�@���̂��߁A�⌾�ɂ����Ĉ�Y�����̋֎~����������A�������ł̐\���ƂȂ�A�[�ŏ�̕s���������邨���ꂪ����܂��B���Ȃ��Ƃ��⌾�ɂ������Y�����̋֎~�́A�Ŗ��I�ɂ݂ėL���ɍ�p���邱�Ƃ͂���܂���B
�@ |
|
|
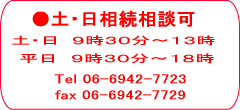

|
|
|
�s����-���������������@
�V�ŗ��m�������@�ŗ��m�@�V�@����
���T�S�O�|�O�O�R�X�@���s�����擌���틴�Q�|�Q�S�|�Q�O�P
�s�d�k�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�R�@�e�`�w�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�X
�@�d���������F���������V�V�Q�R�������R�D�����|�������D�����D����
�@Co���������������i���j2006�r�������s�����`�������������������n�����������D�`�����q�����������q���������������D |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |