| �����K�͑�n���ɂ��Ẳېʼn��i�̌v�Z�I |
�����K�͑�n���ɂ��Ẳېʼn��i�̌v�Z�̓���
�P.����̎�|�ƊT�v
�@�����ł́A���Y�̎擾�ɂ�����łł��邱�Ƃ���A�y�n�Ȃǂ̕s���Y�����𑊑�����ƁA���̕s���Y�p���Ȃ��Ɣ[�Ŏ���������Ȃ��Ƃ����P�[�X������܂��B
�@�Ƃ��낪�A���̓y�n�Ŏ��Ƃ��s���Ă�����A�����l����������Z�ݑ�����y�n�́A�����̊�ՂɂȂ���Y�ł���A�����ł̂��߂ɏ�������Ɛ����̈ێ����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�@�����ŁA���̎��Ɨp�̓y�n�⋏�Z�p�̓y�n�ɂ��ẮA���̂����u���x�ʐϗv���v���������ɂ��āA�ʏ�̕]���z�����芄�������z���đ����ł̉ېŊz�Ƃ��邱�Ƃɂ��Ă���B
�@������u���K�͑�n���ɂ��đ����ł̉ېʼn��i�̌v�Z�̓���v�Ƃ����܂��B
�Q�D���K�͑�n���̈Ӌ`
�@�l��������②�ɂ��擾�������Y�̂����ɁA���̑����̊J�n�̒��O�ɂ����āA�푊���l��푊���l�Ɛ��v����ɂ���e���̎��Ƃ̗p���͋��Z�̗p�ɋ�����Ă�����n���i��n���͎ؒn���ȂǑ�n�̏�ɑ����錠���j�Ō������͍\�z���̕~�n�̗p�ɋ�����Ă������̂�����ꍇ�ɂ����āA����Ώۑ�n���ɊY��������̂̂����A���̌l���I���������̂ŁA���x�ʐϗv���������̂����K�͑�n���Ƃ����B
�@�Ȃ��A���̓���́A�����ł̐\�������܂łɑ����l���̊Ԃŕ�������Ă��Ȃ���n���ɂ͓K�p����Ȃ��B
�@�������Y���������̏ꍇ�̉ېʼn��i�̌v�Z���@�́A���̓���ɂ�錸�z�O�̑�n���̕]���z����ɉېʼn��i���v�Z���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�������A�����ł̐\�������ɂ����Ė������ł��A���̑�n������\����������R�N�ȓ����ɕ��������A���̓�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�R�D����̓K�p�Ώۖʐρi���x�ʐϗv���j
�@���̓���̓K�p�ɂ�茸�z������n���̖ʐρi���x�ʐϗv���j�́A����̓K�p�ΏۂƂȂ��n���̎�ނɉ����Ď��̂悤�ɒ�߂��Ă���B
�@���̓���̓K�p������̂Ƃ��đI��������n���i�I�����Ώۑ�n���j�̂��ׂĂ��u���莖�Ɨp����n���v�̏ꍇ�E�E�E�S�O�O�u�܂�
�A�I�����Ώۑ�n���̂��ׂĂ��u���苏�Z�p��n���v�̏ꍇ�E�E�E�Q�S�O�u
�B�I�����Ώۑ�n���̂��ׂĂ��u�ݕt���Ɨp��n���v�̏ꍇ�E�E�E�Q�O�O�u
�C�I�����Ώۑ�n�����u���莖�Ɨp����n���v�A�u���苏�Z�p��n���v�y�сu�ݕt���Ɨp��n���v�̏ꍇ�E�E�E���̎Z���ɂ��v�Z�����ʐς܂�
���莖�Ɨp����n���̍��v�ʐρ{�i���苏�Z�p��n���̍��v�ʐρ~�T�^�R�j�{�i�ݕt���Ɨp��n���̍��v�ʐρ~�Q�j���S�O�O�u
�i���j�P�@��L�́u���莖�Ɨp����n���v�Ƃ́A���L�Ő�������u���莖�Ɨp��n���v�y�сu���蓯����Ў��Ɨp��n���v�������܂��B
�@�Q�@��L�̇C�̎Z���́A���莖�Ɨp����n���A���苏�Z�p��n���y�ёݕt���Ɨp��n���̂����A�Q�ȏ�̎�ނ̂��̂�I�����Ώۑ�n���Ƃ����ꍇ�̂��ꂼ��̑�n���̌��x�ʐς̒����v�Z�ł���A���̎Z���͎��̂悤�ɏ����������Ƃ��ł��܂��B
�C�@�I�����Ώۑ�n�������莖�Ɨp����n���Ɠ��苏�Z�p��n���ŁA���莖�Ɨp����n����D�悵�đI�������ꍇ�̓��苏�Z�p��n���̓K�p�ʐ�
�@���苏�Z�p��n���̓K�p�ʐρ��Q�S�O�u�|�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ������莖�Ɨp����n���̖ʐρ~�R�^�T�j
���@�I�����Ώۑ�n�������莖�Ɨp����n���Ɠ��苏�Z�p��n���ŁA���苏�Z�p��n����D�悵�đI�������ꍇ�̓��莖�Ɨp����n���̓K�p�ʐ�
�@���莖�Ɨp����n���̓K�p�ʐρ��S�O�O�u�|�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ������苏�Z�p��n���~�T�^�R�j
�n�@�I�����Ώۑ�n�������莖�Ɨp����n���Ƒݕt���Ɨp��n���ŁA�ݕt���Ɨp��n����D�悵�đI�������ꍇ�̑ݕt���Ɨp��n���̓K�p�ʐ�
�@�ݕt���Ɨp��n���̓K�p�ʐρ��Q�O�O�u�|�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ������莖�Ɨp����n���̖ʐρ~�P�^�Q�j
�j�@�I�����Ώۑ�n�������莖�Ɨp����n���Ƒݕt���Ɨp��n���ŁA�ݕt���Ɨp��n����D�悵�đI�������ꍇ�̓��莖�Ɨp����n���̓K�p�ʐ�
�@���莖�Ɨp����n���̓K�p�ʐρ��S�O�O�u�|�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ����ݕt���Ɨp��n���̖ʐρ~�Q�j
�z�@�I�����Ώۑ�n�������苏�Z�p��n���Ƒݕt���Ɨp��n���ŁA���苏�Z�p��n����D�悵�đI�������ꍇ�̑ݕt���Ɨp��n���̓K�p�ʐ�
�@�ݕt���Ɨp��n���̓K�p�ʐρ��Q�O�O�u�|�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ������苏�Z�p��n���̖ʐρ~�Q�D�T�^�R�j
�w�@�I�����Ώۑ�n�������苏�Z�p��n���Ƒݕt���Ɨp��n���ŁA�ݕt���Ɨp��n����D�悵�đI�������ꍇ�̓��苏�Z�p��n���̓K�p�ʐ�
�@���苏�Z�p��n���̓K�p�ʐρ��Q�S�O�u�|�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ����ݕt���Ɨp��n���̖ʐρ~�R�^�Q�D�T�j
�g�@�I�����Ώۑ�n�������莖�Ɨp����n���A���苏�Z�p��n���y�ёݕt���Ɨp��n���ŁA���莖�Ɨp����n���Ɠ��苏�Z�p��n����D�悵�đI�������ꍇ�̑ݕt���Ɨp��n���̓K�p�ʐ�
�@�ݕt���Ɨp��n���̓K�p�ʐρ��Q�O�O�u�|�o�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ������莖�Ɨp����n���̖ʐρ~�P�^�Q�j�{�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ������苏�Z�p��n���̖ʐρ~�Q�D�T�^�R�j�p
�`�@�I�����Ώۑ�n�������莖�Ɨp����n���A���苏�Z�p��n���y�ёݕt���Ɨp��n���ŁA���莖�Ɨp����n���Ƒݕt���Ɨp��n����D�悵�đI�������ꍇ�̓��苏�Z�p��n���̓K�p�ʐ�
�@���苏�Z�p��n���̓K�p�ʐρ��Q�S�O�u�|�o�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ������莖�Ɨp����n���̖ʐρ~�R�^�T�j�{�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ����ݕt���Ɨp��n���̖ʐρ~�R�^�Q�D�T�j�p
���@�I�����Ώۑ�n�������莖�Ɨp����n���A���苏�Z�p��n���y�ёݕt���Ɨp��n���ŁA���苏�Z�p��n���Ƒݕt���Ɨp��n����D�悵�đI�������ꍇ�̓��莖�Ɨp����n���̓K�p�ʐ�
�@���莖�Ɨp����n���̓K�p�ʐρ��S�O�O�u�|�o�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ������苏�Z�p��n���̖ʐρ~�T�^�R�j�{�i�I�����Ώۑ�n���Ƃ����ݕt���Ɨp��n���̖ʐρ~�Q�j�p
�S�@���z�̊���
�@���̓��Ⴊ�K�p�����ꍇ�̑����ł̉ېʼn��i�ɎZ���������z�́A���K�͑�n���̉��z�i�]���z�j�Ɏ��̊������悶�����z�ł���B
�@���莖�Ɨp��n���A���苏�Z�p��n���y�ѓ��蓯����Ў��Ɨp��n���ł��鏬�K�͑�n���E�E�E�P�O�O���̂Q�O
�A�ݕt���Ɨp��n���ł��鏬�K�͑�n���E�E�E�P�O�O���̂T�O
�@�܂�A�@�ɊY�����鏬�K�͑�n���͒ʏ�̕]���z����W�O�����z�A�܂��A�A�̏ꍇ�͂T�O�����z�����Ƃ������Ƃł��B
�@���K�p�Ώۖʐςƌ��z�������܂Ƃ߂�ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B
| ���K�͑�n���̎�� |
�K�p�ʐ� |
���z���� |
| ���莖�Ɨp����n�� |
���莖�Ɨp��n�� |
�S�O�O�u |
�W�O�� |
| ���蓯����Ў��Ɨp��n�� |
�S�O�O�u |
�W�O�� |
| ���苏�Z�p��n�� |
�Q�S�O�u |
�W�O�� |
| �ݕt���Ɨp��n�� |
�Q�O�O�u |
�T�O�� |
(���j���苏�Z�p��n���ɌW�����̓K�p�Ώۖʐς̊g��
�@���s�F�@����Q�S�O�u����@����āF�@����R�R�O�u�ɉ���B�i�����Q�V�N�P���P���ȍ~�K�p�j
�i���j���莖�Ɨp�Ɠ��苏�Z�p�̑�n�p����ꍇ�̌��x�ʐ�
�@���s�F�@���Ɨp�F�S�O�O�u�@���Z�p�F�Q�S�O�u�@�ő�S�O�O�u
�@����āF���Ɨp�F�S�O�O�u�@���Z�p�F�R�R�O�u�@�ő�V�R�O�u�i�����Q�V�N�P���P���ȍ~�K�p�j
�@�Ȃ��A��L�̊e��n����푊���l�̕����̐e���ɂ���ċ����i���L�j�Ŏ擾�����ꍇ�ɂ́A���莖�Ɨp��n���A���蓯����Ў��Ɨp��n���A���苏�Z�p��n�����͑ݕt���Ɨp��n���̗v�������҂̎擾���������̊����ɉ����镔���ɓK�p����܂��B
�T�D����Ώۑ�n���̈Ӌ`
�@���̓���ɂ�錸�z�����́A���莖�Ɨp��n���A���蓯����Ў��Ɨp��n�����͓��苏�Z�p��n���ɂ��ĂW�O���A�ݕt���Ɨp��n���ɂ��Ă͂T�O���ł��邪�A���ꂼ��̓K�p�v�������҂��擾�����ꍇ�Ɍ���A���Ⴊ�K�p����܂��B
(�P)���莖�Ɨp��n��
�@�푊���l���̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă�����n���ŁA���̗v���̂����ꂩ�����푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾�������̂������B
�@���̐e���������J�n�����瑊���ł̐\�������܂ł̊ԂɁA���̑�n���̏�ʼnc�܂�Ă����푊���l�̎��Ƃ������p���A�\�������܂ł��̑�n�������L���A���A���̎��Ƃ��c��ł��邱�ƁB
�A���̐e�������̔푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă����҂ł����āA�����J�n�����瑊���ł̐\�������܂ň����������̑�n�������Ȃ̎��Ƃ̗p�ɋ����Ă��邱�ƁB
�@���̂����@�́A�푊���l�̎��Ɨp��n�����擾���������l�����A���̑�����ɔ푊���l�̎��Ƃ������p�����Ƃ����P�[�X�ł���A�����ǂ��葊���ɂ�鎖�ƌp����z�肵�����̂ł���܂��B
�@����ɑ��A�A�ɂ�����u���ȁv�Ƃ́A��n�����擾���������l��������̎��Ƃ��s���Ă����P�[�X���z�肳��Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���莖�Ɨp��n���ɂ�����u���Ɓv�ɂ́A������s���Y�ݕt�Ƃ͊܂܂�Ȃ��B���������āA�ݑ�n��݉ƌ��t���n�ɂ��ẮA�ݕt���Ɨp��n���ɊY������ꍇ�Ɍ���A���z�̊������T�O���ƂȂ�B
�i�Q�j���苏�Z�p��n��
�@�푊���l���̋��Z�̗p�ɋ�����Ă�����n���ŁA�푊���l�̔z��Җ��͎��̗v���̂����ꂩ�����푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾�������̂������܂��B
�@���̐e���������J�n�̒��O�ɂ����āA���̑�n���̏�ɑ�����푊���l�̋��Z�p�Ɖ��ɋ��Z���Ă����҂ł����āA�����J�n�����瑊���ł̐\�������܂ň����������̑�n�������L���A���A���̉Ɖ��ɋ��Z���Ă��邱�ƁB
�A���̐e���������J�n�O�R�N�ȓ��ɂ��̎Җ��͂��̔z��҂̏��L����Ɖ��ɋ��Z�������Ƃ��Ȃ��҂ł���A���A�����J�n�����瑊���ł̐\�������܂ň����������̑�n�������L���Ă��邱�Ɓi�푊���l�̔z��Җ��͓����̖@�葊���l�����Ȃ��ꍇ�Ɍ���B�j
�B���̐e�����푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă����҂ł����āA�����J�n�����瑊���ł̐\�������܂ň����������̑�n�������L���A���A�����J�n�O����\�������܂ň����������̑�n�������Ȃ̋��Z�̗p�ɋ����Ă��邱�ƁB
�@�v����ɁA�z��҂����Z�p��n���𑊑������ꍇ�́A�������łW�O�����z���F�߂��邪�A�q�ȂǑ��̑����l���擾�����ꍇ�́A�@����B�̂����ꂩ�ɊY�����Ȃ��ƂW�O�����z�͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@�Ȃ��A�푊���l���̋��Z�̗p�ɋ�����Ă�����n�����Q�ȏ゠��ꍇ�ɂ́A���̑�n�������苏�Z�p��n���ƂȂ�B
�@�푊���l�̋��Z�p��n�����Q�ȏ゠��ꍇ�E�E�E���̔푊���l����Ƃ��ċ��Z�̗p�ɋ����Ă�����̑�n��
�A�푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă����e���̋��Z�p��n�����Q�ȏ゠��ꍇ�E�E�E���̐e������Ƃ��ċ��Z�̗p�ɋ����Ă�����̑�n��
�B�푊���l�y�т��̔푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă����e���̋��Z�p��n�����Q�ȏ゠��ꍇ�E�E�E
���̋敪�ɉ����A���ꂼ��ɒ�߂��n��
�C�@���̔푊���l����Ƃ��ċ��Z�̗p�ɋ����Ă�����̑�n���Ƃ��̐e������Ƃ��ċ��Z�̗p�ɋ����Ă�����̑�n���Ƃ�����ł���ꍇ�E�E�E���̈�̑�n��
���@�C�ȊO�̏ꍇ�E�E�E���̔푊���l����Ƃ��ċ��Z�̗p�ɋ����Ă�����̑�n���y�т��̐e������Ƃ��ċ��Z�̗p�ɋ����Ă�����̑�n��
�@�v����ɁA����̑ΏۂƂȂ���苏�Z�p��n���́A�P�����Ɍ�����Ƃ������Ƃł��B
�i�R�j���蓯����Ў��Ɨp��n��
�@�����J�n�̒��O�ɂ����Ĕ푊���l�y�т��̔푊���l�̓����W�҂��L���銔���i�o�����܂ށj�̑��������̖@�l�̔��s�ϊ��������i�o�����z�j�̂P�O���̂T����@�l�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă�����n���ŁA���̑�n���𑊑����͈②�ɂ��擾�����푊���l�̐e���i�����ł̐\�������ɂ����Ă��̖@�l�̖����ł���҂Ɍ�����j�������J�n������\�������܂ň����������L���A���A�\�������܂ň����������̖@�l�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă�����̂������B
�@�Ȃ��A���̏ꍇ�̖@�l�́u���Ɓv�ɂ͕s���Y�ݕt�Ƃ͊܂܂�Ȃ��B���������āA�@�l�̎��Ƃ��s���Y�ݕt�Ƃł���ꍇ�ɂ́A�W�O�����z�͓K�p����Ȃ��B
�i�S�j�ݕt���Ɨp��n��
�@�푊���l���̑ݕt���Ƃ̗p�ɋ�����Ă�����n���ŁA���̗v���̂����ꂩ�����푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾�������̂������B
�@���̐e���������J�n�����瑊���ł̐\�������܂ł̊ԂɁA���̑�n���ɌW��푊���l�̑ݕt���Ƃ������p���A���̐\�������܂ň����������̑�n�������L���A���A���̑ݕt���Ƃ̗p�ɋ����Ă��邱�ƁB
�A���̔푊���l�̐e�����푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă����҂ł����āA�����J�n�����瑊���ł̐\�������܂ň����������̑�n�������L���A���A�����J�n�O���瑊���ł̐\�������܂ň����������̑�n�������Ȃ̑ݕt���Ƃ̗p�ɋ�����Ă��邱�ƁB
�@�����́A���莖�Ɨp��n���́u���Ɓv���u�ݕt���Ɓv�Ƃ����ꍇ�̗v���Ɠ����ł��B�v����ɇ@�́A�푊���l�̕s���Y�ݕt�ɌW���n�����擾���������l�����A������ɂ��̑ݕt���Ƃ����p�����P�[�X�ł���A�A�́A��n�����擾���������l�����A�푊���l�̏��L�����n���ŁA�����J�n�O����ݕt���Ƃ��s���Ă���A����������̑ݕt���Ƃ��p������Ƃ������Ƃł���B
�@�Ȃ��A���̋K��ɂ�����u�ݕt���Ɓv�Ƃ́A�u�s���Y�ݕt�ƁA���ԏ�ƁA���]�Ԓ��ԏ�y�ю��ƂƏ̂���Ɏ���Ȃ��s���Y�̑ݕt�����̑�����ɗނ���s�ׂő����̑Ή��Čp���I�ɍs�����́v�Ƃ���Ă��܂��B
�@���������āA������݉ƌ��t�n��ݑ�n���ݕt���Ɨp��n���Ƃ��ē���̑ΏۂƂȂ邪�A���莖�Ɨp��n���ƈقȂ�A�W�O���z�ł͂Ȃ��A�T�O���z�ƂȂ邱�Ƃɒ��ӂ�v���܂��B
�U�D������邽�߂̐\���葱��
�@���K�͑�n���ɂ��Ẳېʼn��i�̌v�Z�̓�����邽�߂ɂ́A�����Ƃ��đ����ł̐\�����ɁA���̋K��̓K�p���悤�Ƃ���|���L�ڂ��A�ېʼn��i�Z���z�Ɋւ��閾�����̑����̏��ނ�Y�t���邱�ƂƂ���Ă��܂��B
|
|
|
�� ����̎�|�ƊT�v
�� ���K�͑�n���̈Ӌ`
�� ����̓K�p�Ώۖʐρi���x�ʐϗv���j
�� ���z�̊���
�� ���莖�Ɨp��n��
�� ���苏�Z�p��n��
�� ���蓯����Ў��Ɨp��n��
�� �ݕt���Ɨp��n��
�� ������邽�߂̐\���葱���@ |
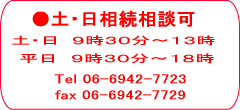

�@ |
|
|
�s����-���������������@
�V�ŗ��m�������@�ŗ��m�@�V�@����
���T�S�O�|�O�O�R�X�@���s�����擌���틴�Q�|�Q�S�|�Q�O�P
�s�d�k�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�R�@�e�`�w�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�X
�@�d���������F���������V�V�Q�R�������R�D�����|�������D�����D����
�@Co���������������i���j2006�r�������s�����`�������������������n�����������D�`�����q�����������q���������������D |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |