| ���s���Y���݂͖@�l�����L�� |
�@���@�s���Y���݂͖@�l���`���L��
�@�푊���l�̓y�n�̏�ɖ@�l���`�̒��ݏZ������݂��A�s���Y�Ǘ���Ђ����p����
���Ƃɂ��A�����������܂ŁA�푊���l�̍��Y�𑝂₳���ɁA�����l�̔[�Ŏ�����
�m�ۂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@
�������b�g
�@�@�@�����W�҂���Ђ̖����ɏA�C�����邱�Ƃɂ��A������V���Ƃ�܂��̂ŁA
�e�����l�ɏ����U���A�[�Ŏ������m�ۂł��܂��B
�@
�@�A�@�����S���ɐ����ی����|���邱�ƂŔ푊���l�i���j�⑊���l�̑ސE����
�������ł��܂��B
�@
�@�B�@�푊���l�i���j�A�Ȃ́A����ɂȂ��Ă��Ȃ����ߕs���Y�Ǘ���ЂɎ��Y��
�����瑝���Ă��A�푊���l��z��҂̑������Y�͑����܂���B
�@
�@�C�@������V�́A�푊���l�i���j�A�ȁA���j�A���j�̍ȁA��A��5���Ɏx�����̂�
�������U�ƂQ��������ɂȂ�܂��B
�@
�@�D�@���̗v���ɊY������ƒ��ݏZ��݂ɌW�����ł̊ҕt���邱�Ƃ�
�ł��܂��B
�@
|
A�������
���ݏZ��
�i�s���Y�Ǘ���Ёj
|
|
| �푊���l�i�y�n�j |
| �� |
���i������j
�@�i������V�E���ہj |
�@ |
��i�����
�@�i������V�E���ہj |
|
|
| �@ |
|
|
|
|
���j�i������j
�@�@�@�i����j
�i������V�E���ہj |
�@ |
�ȁi������j
�@�@�i����j
�i������V�E���ہj |
|
�@ |
|
|
|
�@ |
|
|
��A�i������j
�@�@�i����j
�i������V�E���ہj |
|
|
��B |
|
|
�@
���f�����b�g
�@�@�푊���l�i���j�����݂��邱�Ƃɂ��݉Ƃ̕]�������g���܂���B
�@�A�푊���l�i���j�����ݏZ��݂����Ȃ��̂ŁA�ؓ��������Ȃ�
�@�@���ߑ����ł̍��T�����g���܂���B
�@
�k��l�@�푊���l�i���j�l�Œ��ݏZ������z�����ꍇ
�@�@�@�E�~�n�̕]���@10,000���~
�@�@�@�E�����]���z�@7,000���~
�@�@�@�E���z���z�@�@12,000���~
�@�@�@�E�ؓ����@�@�@12,000���~
�@�@�@�E���ݎ����@��1,000���~
�@
�@�@���ݏZ��̕~�n�����z����܂��B�i�ؒn��60���j
�@�@�@10,000���~�~�i1�|0.6�~0.3�j��8,200���~
�@
�@�A�����̕]���z�i�Œ莑�Y�ŕ]���z�j��30�����z�����B
�@�@�@7,000���~�~�i1�|0.3�j��4,900���~
�@
�@�B�ؓ����z�@�@12,000���~
�@
�@�C���ݎ������N1,000���~��������B
�@
�@�D�ߐŌ��ʂɂ�葊�����Y��15,900���~���z�ɂȂ�܂��B
| �i10,000���~�|8,200���~�j�{�i7,000���~�|4,900���~�j�{12,000���~��15,900���~ |
�@
�@�����ݏZ����l�Ō��z�����ꍇ�A10�N���炢�܂ł́A���|�I�ɐߐ�
�@�@���ʂ͑傫���ł����A���N���Z�������ݎ����N�ԍς�����
�@�@�����̌����ɂ���Č��z��20�N������t�ɑ������Y���������邱��
�@�@�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�@���̂��ߒ����ɂ킽��ߐł����l���̕��͖@�l�ɂ�錚�z���L���ł��B
�@
�k��l�@�l�ɂ����ݏZ������z�����ꍇ
�@�@�@�@���ݏZ��̕~�n�̕]��
�@�@�@�@10,000���~�~80����8,000���~
�@
�@�@�A�@�����̕]���z�i�Œ莑�Y�]���z�j�͌��z����܂���
�@�@�@�@7,000���~�~1��7,000���~
�@
�@�@�B���ݎ���1,000���~���s���Y�Ǘ���ЂƂȂ�l��0�~�ƂȂ�B
�@
�@�@�C�푊���l�i���j�ɒn��������������܂��B�i��߂ɐݒ肷��j
�@
�@�@�D�푊���l�i���j�ɂ͖�����V���������܂��B
�@
�@�@�E�ؓ�����0�~
�@
�@�@�F�ߐŌ��ʂɂ�葊���ł̉ېō��Y��2,000���~���z�ɂȂ�܂��B
�@�@�@10,000���~�|8,000���~��2,000���~
|
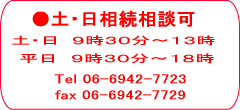

|
|
|
|
|
�s����-���������������@
�V�ŗ��m�������@�ŗ��m�@�V�@����
���T�S�O�|�O�O�R�X�@���s�����擌���틴�Q�|�Q�S�|�Q�O�P
�s�d�k�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�R�@�e�`�w�O�U�|�U�X�S�Q�|�V�V�Q�X
�@�d���������F���������V�V�Q�R�������R�D�����|�������D�����D����
�@Co���������������i���j2006�r�������s�����`�������������������n�����������D�`�����q�����������q���������������D |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|