●不動産相続の節税対策と進め方
|
■不動産相続の節税対策と進め方
1.不動産相続の節税の進め方
相続人間でリーダーを決めて、相続対策の目標を定めます。
不動産の有効利用や生前贈与をどのように活用するのか、相続税がいくら
かかるのか、遺産分割はどのようにするのかなどを決め、具体的に進めて
いきます。
次にその提案書を作り、親にも説明して納得をしてもらいます。提案書では、
資産の使用状況や相続税の見込み額、親の意向を踏まえて遺産分割のやり方や
相続税対策の内容を説明します。その提案書を親が納得したら具体的に生前
贈与を行い不動産の組み替えや遺言書を書いてもらったりします。
その際には親の意思能力を必ず確認して証拠を残すようにします。これは
後々税務調査で突っ込まれたり、相続人間のトラブルになったりするのを防ぐ
ため、意思能力の確認は非常に重要ですので必ず行うようにして下さい。
2.節税は不動産等を減らして節税するか、財産評価を落として節税するか
どちらかに該当する
不動産等の資産を減らして節税につなげる方法は例えば親が財産を使いたい
放題つかい財産を減らし相続税を減らす方法です。また、生前贈与も相続人
などに財産を移転することになり、減らして節税させるものになります。その際
贈与税の非課税枠をうまく利用すれば効果的な資産移転が可能です。
他の一つは資産を減らすのではなく財産評価を落とすことより節税に結び
つける方法です。これは資産を組み替えたりすることで、評価を下げるものです。
相続税は国が定めた評価額をもとに相続税額が計算されます。資産の評価額は
あくまでも国が定めるものであり市場における実際の取引価格との差を利用し
相続税の負担を抑えるものです。
例えば資産のうち現金が1億円あるとしたら、その資産は額面通り1億円ですが、
不動産に変えれば、評価額が2,000万円になる場合もあります。
3.相続資産1億円以下は大掛かりな節税対策は必要なし
資産が1億円以下の場合、無理して節税のために不動産を購入必要は
ありません。資産が1億円として相続人が配偶者と子2人のケースですと、
基礎控除額が4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。
単純計算しますと残り5,200万円となり、相続税の計算をしますと、
630万円になります。配偶者は配偶者の税額控除があり、相続税税額が0円に
なり、実質290万円が相続税です。1億円の不動産を購入すると仲介手数料など
で、500万円以上かかりますので購入しない方は得策です。
4.相続資産1億円以下の効果的な生前贈与のやり方
(1)暦年贈与
これは、以前から使われている方法でお一人年間110万円まで非課税です。
また、2015年から新しく「特別税率」が設けられいます。
直系尊属が20歳以上の子や孫などに対して贈与した財産を「特例贈与財産」と
呼び一般的の贈与と異なる税率を適用するのが「特例税率」です。最高税率は
55%と同じですが、累進性が一般的の贈与よりゆるやかになっていますので、
税負担が軽減されています。
(2)相続時精算課税
2003年に施行された制度で親子間の贈与については軽減しつつ親が亡く
なったときに、今までの贈与を相続財産に含めて相続税の申告をする制度です。
(イ)贈与者(父または母)は1人当たりの贈与金額が合計2,500万円を超える
までは、.贈与税が非課税です。
(ロ)2,500万円を超えても一律20%の贈与税を支払います。
(ニ)贈与者が亡くなったときは、それまで贈与した財産の価額と相続財産の
価額を合計した金額をもとに計算した相続税からすでに納付済みの贈与税額
相当額を控除します。
(ニ)暦年課税なや110万円の基礎控除をフル活用できる
節税対策で暦年課税と相続時精算課税で生前贈与対策なら、暦年課税を
お勧めします。
その理由は、相続時精算課税は贈与者ごとの2,500万円までの特別控除
ですが、、これは贈与した資産に税金が全くかからないということでは、
おりません。相続が発生したときに精算するのです。また、この方式は、贈与者
ごとにいったん選択するとそれ以降は、その贈与者が亡くなるまでずっとそのまま
続けなければなりません。暦年課税に戻ることはできません。もう一つの問題は、
相続時の精算において相続財産と合算する贈与財産の評価額は贈与時の価額に
なるため贈与時点から評価額が上がっていれば有利ですが、逆に値下がりすると
不利になり税の負担が増加します。よほどの理由でたとえば自社株対策で株価を
下げた株を生前に贈与するなどの理由がないかぎり相続時精算課税はお勧めで
きません。
それに対し暦年課税では毎年110万円の非課税枠があります。1年たった
110万円と思われるかもしれませんが、5年、10年という期間で考えてはどうで
しょうか。
金融資産1億円の場合、配偶者、子2人のケースの場合、年330万円×10年
=3,300万円 20年で6,600万円の生前贈与ができます。
(1億円ー3,300万円)−4,800万円=1,900万円が課税資産になり、
ぐっと相続財産を減らすことができます。
また、住宅資金として1,000万円(耐震、エコ住宅で1,500万円)、教育資金
として1,500万円をそれぞれ非課税で子供などに贈与できる特例もありますから
それらを併せて利用すれば相続税がかからなくなります。
|
|
|
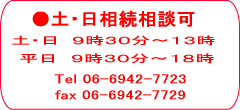

|
|
|
Tax-station
澤税理士事務所 税理士 澤 眞次
〒540−0039 大阪市中央区東高麗橋2−24−201
TEL06−6942−7723 FAX06−6942−7729
Email:sawa7723@za3.so−net.ne.jp
Copyright(c)2006SawaTaxAccountantOffice.AllRightsReserved. |
|